放送日時:3月5日(水)21:00~
【放送内容】
・残りわずかになった国民的企業を徹底取材☆
・昭和世代憧れの地球儀の最新版は激ヤバ!
・パチパチ弾けるあの駄菓子の裏側とは?
・全焼火災から復活を遂げた企業秘話☆
≪出演者≫
【MC】内村光良
【リアクター代表】大竹一樹(さまぁ〜ず)
【語り手代表】千原ジュニア
【語り手】 アンミカ、伊集院光、カンニング竹山、東京ホテイソン、山田真哉
【ゲスト】 みちょぱ
【ロケ出演】ゴー☆ジャス
今回は「何を隠そう…ソレが!」の中で紹介される「絶滅危惧企業」を、ここでもランキング形式でご紹介いたします☆
経済のプロが約2か月間、全国200社を調査しランキングを作成☆
見ていくと「そういえばその企業ってどうなった??」というような感覚になりそうですね☆
以下から見ていきましょう☆
▼番組の情報はこちらからご覧いただけます▼
愛すべき国産絶滅危惧企業 ランキングでご紹介☆
1位 アトリオン製菓【わたパチ】
2位 鈴木楽器製作所【鍵盤ハーモニカ】
3位 長村製作所【電話ボックス】
4位 戸田商行【もくめん】
5位 菊水産業【爪楊枝】
6位 渡辺教具製作所【地球儀】
では、ここから一つずつ見ていきましょう☆
第6位 渡辺教具製作所【地球儀】
1937年に渡辺雲晴氏が創業、埼玉県草加市にある渡辺教具製作所で制作されているのは、小学生憧れの勉強グッズ「地球儀」です☆
現在は5代目が継承されています☆
以前はメーカーが数社あったのですが、今は3社に激減…
地球儀メーカーが減っていく中、なぜ生き残れたのか…その理由は、他には真似できない圧倒的な技術が☆
それは、紙製の地球儀を機械量産できるマシンを使っているところです☆
このマシンを持っているのは世界に2社しかないそうで、もう1社はアメリカの企業が所持しているとの事☆
海外製品の地球儀の多くは、地図の書かれたプラスチックのフィルムを伸ばして作るのですが、それだとどうしても地図に歪みが出てしまうんだそう。
しかし、紙で作ると細部の歪みが少なく、そのままの縮尺で印刷が可能☆
ちなみに、より正確のものにするため、衛星写真をチェックし3年に1度更新☆
さらに、独立などで国名や都市名が変わる事があり、そのたびに地図をアップデート☆
こんな精度の高い地球儀を作れるからこそ、今でも生き残れているのですね☆
また、渡辺教具製作所はその技術力を生かし様々な地球儀を開発☆
一般的な地球儀は直径26cmなのですが、その2倍ほどの直径45cmの地球儀も制作☆
学校などに設置されているそうです☆
直径26cmのものは14,850円(税込)なのに対し、直径45cmのものは198,000円(税込み)と10倍以上!
また、直径100cmの地球儀もイベント用として制作しているそうです☆(お値段は要相談)
過去には、東京のホテルから「ロビーに【国境のない国名だけ入っている地球儀】を飾りたい」と制作依頼があり、制作しました。
これは、国により国境の考え方が違うためで、様々な国から観光客が訪れるホテル側としては「お客様に不愉快な思いをさせたくない」という想いからのオーダーだったようですね☆
さらに、この自慢の技術力で新たな地球儀の制作に成功☆
それは「ほぼ日のアーズボールジャーニー」です☆
この地球儀をスマホや専用アプリで見ると、8種類の恐竜が見えたり、その地域の現在の天気が見れたり、各国のデータを確認する事が出来るのです☆
これは一度手にしてみたいと思ってしまいました☆
第5位 菊水産業【爪楊枝】
大阪府 河内長野市にある「菊水産業」で制作されているのは、およそ1300年お口の健康を守る「爪楊枝」を制作されている企業です☆
お口の健康だけでなく料理にも欠かせない爪楊枝ですが、日本に伝わってきたのは奈良時代☆
当時の木を繊維状にしたものが原点です。
江戸時代には長さ約20cmほどの長さでしたが、後期になると急激にコンパクトに☆
形も、うなぎや白魚・てっぽうやきせるなど、職人がその腕を競うものでもありました☆
大正時代には機械による大量生産が可能となり、現在の掘り込みの入った爪楊枝が主流となりました☆
ちなみに、爪楊枝の上の部分にある掘り込みは「制作過程で発生する焦げの部分を目立たないように紛らわせるため」だそうです☆
加工する際に高速回転させ削る工程で、摩擦で黒く焦げ見た目が悪くなるそうです☆
そこで、焦げをこけし人形の頭に似せて溝をつけごまかしたとの事です☆
その部分を折って箸置きのようにすると大半の方は答えられるそうなのですが、どうやら違うようですね…(笑)
この、こけし楊枝を広めたのが河内長野市だったんですね☆
1980年代、河内長野市が国内シェア95%以上☆爪楊枝界の覇権を握っていました☆
しかし1990年代、安価な爪楊枝が日本に上陸し、当時24社あった企業が2社にまで激減…
こけし楊枝の機械メーカーも廃業…
さらに現在の4代目が就任した1位か月後には工場が火事になり、事務所は全焼…
一瞬にしてすべてを失ってしまったのです…
ただ、奇跡的に残ったのが、爪楊枝を製造する特殊な機械だったのです!!
そこで、国産爪楊枝を絶やさぬ為、鎮火の1時間にX(旧ツイッター)にその様子を投稿☆
その投稿にたくさんの「リツイート」や「いいね」がされ、ネット販売しているものが支援として購入されるという状況や、クラウドファンディングをやってほしいという声も多くなり、実際に行ったところ瞬く間に支援を受ける事が出来、その支援金が目標金額の4倍にあたる約1200万円も集まりました☆
こういった後押しもあり、国産の爪楊枝づくりを再開☆
日本の文化を残すべく、今も元気に頑張っています☆
そんな菊水産業が製造している爪楊枝は、以下のリンクから購入可能です☆
菊水産業が製造している他の爪楊枝などは、以下のリンクから見る事が出来ます☆
菊水産業はさらにSDGsにも貢献しています☆
爪楊枝の製造工程で、先が丸くなり使えない商品が出来てしまう事があり、その状態をSNSに投稿☆
すると、それを売ってほしいという声があがり、いわゆる「不良品」が即完売するという事態に☆
なぜ売れたのかというと、先が丸くなった爪楊枝は模型製作の際に細部に接着剤や塗装を行うのにちょうどよい大きさのようで、本来の使用用途以外にも使い道があるという事なんですね☆
爪楊枝、素晴らしいです☆
第4位 有限会社 戸田商行【もくめん】
高知県土佐市にある工場ですが、ここでは「もくめん」というものを製造しています☆
もくめんとは、自然由来の緩衝材の事です☆
昭和40年代には全国に120社以上、もくめんを製造している会社がありましたが、昭和50年代に入るとプラスチック製の緩衝材が台頭!
破竹の勢いで緩衝材の業界を席巻してしまったため、もくめんは衰退の道をたどります…
最終的に現在残っているのは2社のみですが、なぜ生き残れたのでしょうか?
それは、他の緩衝材にはない驚異の保護力を生み出す職人の技術にありました☆
社長に話を聞いたところ、もくめんには湿度を吸湿・放湿する調質機能があるというのです☆
もくめんを箱の中に入れたところ、湿度が55%あったのが、その一時間半後には25%まで低下しました☆
この力があるからこそ、長時間でも果物が傷みにくい状態で輸送可能というわけです☆
もちろん、緩衝材としても超優秀☆
もくめんの入った箱に生卵を入れて、その箱を激しく床に転がしたり投げつけても割れないという高い緩衝力☆
その理由は「薄く切ってカールさせる事」でした☆
カールさせることで、まっすぐのもくめんよりも高いクッション力を発揮するのだそうです☆
カールさせるという技術が、まさに職人の技☆
さらに新商品も開発し、もくめんの可能性を探求☆
カラーもくめんや、木の消臭効果を最大限に活かしたシューズキーパー☆
中でも今話題となってるのが、これまで捨てていた伐採時の枝葉から抽出してつくる「SDGsオイル」☆
杉やヒノキの香りがするエッセンシャルオイルも製造販売☆
是非一度、お試ししてみてはいかがでしょうか?
第3位 長村製作所【電話ボックス】
栃木県栃木市にある長村製作所が制作しているのが「電話ボックス」です☆
昭和では街中で見かけ行列もありましたが、今では約1/8に激減!
全盛期は93万台を超えていたそうですね☆
今、電話ボックスを使用している人はどれくらいいるのか、番組内で独自で調べてみたところ、4か所・30時間でたったの7人。
しかも、利用者の多くは70代の方でした。
利用する理由を尋ねたところ「長電話をすると携帯電話より安いのではないか?」という返答があったそうです。
そんな電話ボックスですが、今後利用者が急増するとは考えにくいですね…
そこで、長村製作所はそのノウハウを生かした新商品で脚光を浴びる事になります☆
それは、電話ボックスの材料を元に使った「個室喫煙ブース」なのだそうです☆
さらに、「リモートワーク用のミーティングブース」を製造☆
最近は会社や駅にも設置されていて、もしかしたら見かけた事がある方も多いかも知れませんね☆
小さなスペースでも設置できるため、人気なのだそうです☆
第2位 鈴木楽器製作所【鍵盤ハーモニカ】
静岡県浜松市にある鈴木楽器製作所で作られているのは「鍵盤ハーモニカ」です☆
以前は鍵盤ハーモニカを製造している会社は4社以上ありましたが、今はこの会社1社のみ!
材料や人件費の高騰で、どんどん製造の拠点は海外へ…
しかし、鈴木楽器製作所はあえて国産にこだわり、ラスト1社の企業となりました☆
そもそも、なぜ小学校で鍵盤ハーモニカを習うのか?
この仕掛けも、この鈴木楽器製作所が大きく関係しています☆
会社の創業は1953年、当時はハーモニカ製造業として始まりました☆
当時の音楽の授業はハーモニカが使われていましたが、演奏する時に口が見えにくくどこを吹いているのかが児童に分かりづらいと苦労があったとの事。
そこで創業者が目をつけたのが、海外で作られた「ボタン式ハーモニカ」☆
これこそ、日本の音楽教育に最適だという事で、国産初の鍵盤ハーモニカを開発☆
1967年には、文部省(当時)が鍵盤ハーモニカを「教材基準」に採用したため、学校の授業で使われる事になりました☆
鍵盤ハーモニカのいい点は、息の入れ方で音色を変えられるところです☆(ゆっくり吹けば優しい音になる など)
息の強さや出し方で音量が変わり、「行動」と「結果」が結び付きやすいというのが、標準教材に採用された理由のようです☆
ちなみに、鍵盤ハーモニカを演奏するのに使用する蛇腹型のマウスピースも、この鈴木楽器製作所が開発したものです☆
その他、鈴木製作所では「汽笛」や「サイレン」など様々な音が鳴るホイッスルの制作もしているという事でした☆
第1位 アトリオン製菓【わたパチ】
1990年ごろに一世を風靡!当時のキッズが衝撃☆
1988年に明治から発売された「わたパチ」☆
口の中でパチパチ弾ける衝撃で、当時のキッズが虜に☆
この「パチパチ」の部分を作っていたのが、長野県須坂市にある「アトリオン製菓」です☆
現在は「パチパチパニック」と名前を変え、今なお子どもたちへの衝撃を提供し続けています☆
このパチパチ、飴の中に超圧縮した炭酸ガスを入れるのですが、この技術を持つのは国内でアトリオン製菓だけです☆
しかし、パチパチパニック販売当初は、売り上げが長らく低空飛行状態…しかし、新たな販売方法で売り上げが10倍に☆
その販売方法は、スーパーやコンビニだけでなく、100円ショップでの販売をはじめたというものでした☆
100円ショップの急増や、「3個で100円」という販売方法が功を奏したという事です☆
さらにこの機を逃すまいとミュージックビデオまで制作!
これは大胆ですね…(笑)
まとめ
今回は「絶滅危惧企業」ということで、6か所の企業を取り上げられていました☆
普段、特別に意識する事のなかった商品でも、「作る側」の視点に立つと色んな歴史や背景が隠れているんだなと改めて実感しました☆
それだけ消費者は安心して生活しているという事だと思っています。
その裏に、こういった企業の頑張りがあるからこその自分たちの生活が成り立っているという事を忘れてはいけないですね☆
それでは、今回はここまで☆
最後までご覧いただきありがとうございました☆
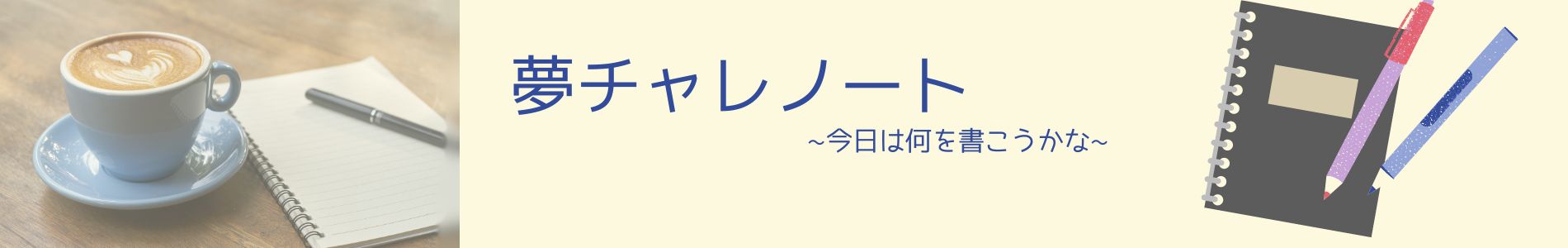

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45a21085.47e887b9.45a21086.bd30e7dc/?me_id=1218200&item_id=10043540&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbungle%2Fcabinet%2Ffile3%2F46804-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45aca6eb.e3543f33.45aca6ec.891d3f20/?me_id=1390598&item_id=10083445&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpro-ste%2Fcabinet%2Fitem-001%2F00019665-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45acd336.370fd54b.45acd337.e05058b9/?me_id=1332653&item_id=10009761&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnipponselect%2Fcabinet%2Fitem%2Ff06%2Ff06950001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45acd242.09f84b98.45acd243.00333d36/?me_id=1374004&item_id=10000302&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff392057-tosa%2Fcabinet%2Fgurume%2Fimgrc0093202458.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45b722b2.940680f2.45b722b3.b32f5afc/?me_id=1356830&item_id=10002293&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fexicoast02%2Fcabinet%2Fmeiji%2Fcompass1696497389.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント